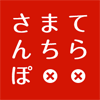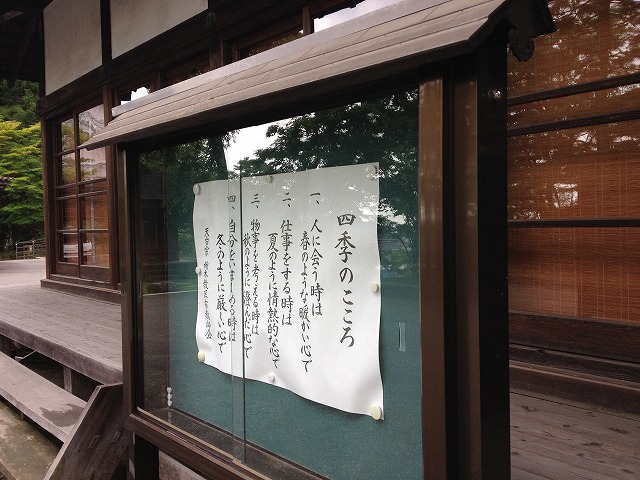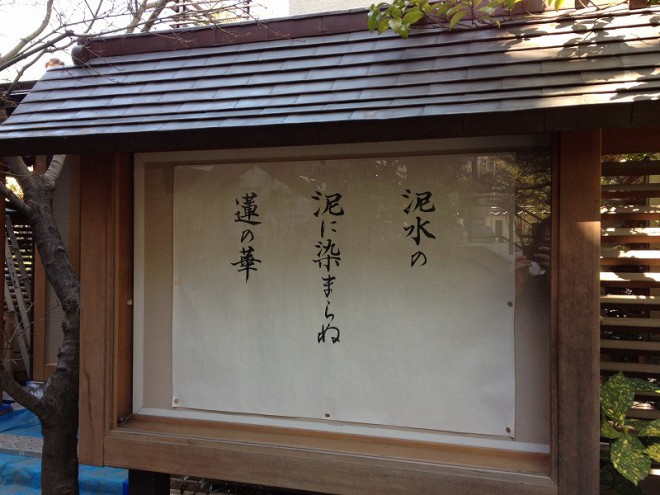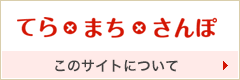てらまちフォト一覧
鹿児島は霧島の麓を走る肥薩線、明治36年開業の嘉例川駅。昭和59年に無人化、平成18年に国の登録有形文化財となる。平成15年の100周年事業は嘉例川地区の人々により開催、これを機に博物館開設、特産品販売、駅弁販売と、駅舎をフル活用しての地区活性化が図られました。今では県内有数の観光スポットとなり、列車に乗らない観光客も、列車の到着時刻に合わせて観光バスでやってくるほど。駅のすぐそばには、屋根つきの共同墓地があり、そこに人々の営みがあることを知らせてくれます。お弁当と一緒に販売されていた「かきあげ」を1個買い求め、列車に乗り込んでからほおばりました。サックリとして甘く、110歳の駅舎と同様に懐かしさを感じました。(参考:広報きりしまNo.40 2007.9)
111年目の肥薩線嘉例川駅
2014年10月22日公開 2014年09月27日撮影
きょうの1枚はお寺でなく神社です。前から気になっていた「べったら市」。今年はついに足を運んでみました。もとは寶田恵比寿神社の恵比寿講だとか。最寄はJR新日本橋駅。夕刻17時過ぎ、首都高下の交差点を渡るともう賑わいが。一帯の路地には露店がずらり。べったら漬けを扱う店はこれでもかと並んでいて、吟味しながら好みの1本を選べます。お店の違いだけでなく、皮付きと皮なしで味も食感も異なるんですね。ほかにも、盆踊りを催していたり、地元の飲食店が自慢のメニューを出していたり、立ち飲みスペースができていたり。こんなに多くの露店が並ぶのは、そうないのでは? 大人も子供も、お国も問わず愉しめそうです。べったら市は毎年10月19、20日に開催。
露店がずらり、日本橋べったら市
2014年10月20日公開 2014年10月19日撮影
鹿児島では明治維新後の廃仏毀釈が殊に厳しく行われたため、南林寺町や慈眼寺など地名や駅名として残っていても、廃寺となった場合が多いようです。写真は不断光院。ここは薩英戦争での誤認による砲撃(文久3年・1863)、廃仏毀釈(明治3年・1870~)、太平洋戦争での空襲(昭和20年・1945)を経て再興してきたお寺。仁王像は、廃仏毀釈の際に隠蔽されたために残ったものだそうです。長年風雨にもさらされ、細かな造作はうしなわれていますが、大ぶりでごつごつとして、愛嬌すら感じられるその姿は、近代的な山門や本殿と対照的で、印象に残りました。
薩英戦争、廃仏毀釈、太平洋戦争を経験した仁王像
2014年10月15日公開 2014年09月28日撮影